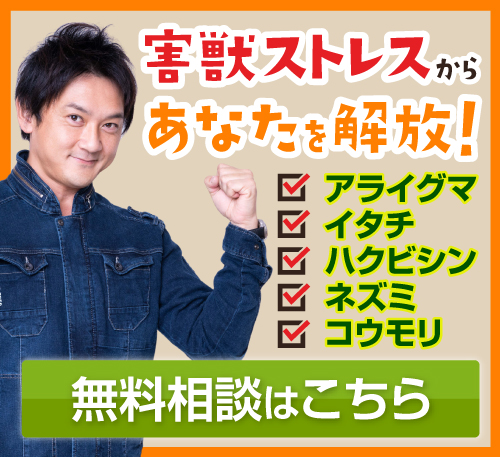「屋根裏から音がするけど、もしかして動物が住み着いているのでは?」と不安になっていませんか。屋根裏は一日中薄暗く、断熱材によって温かい環境ができているため、害獣にとっては最高の住処です。
もし本当に害獣が住み着いていた場合、放置すると家や住民への被害がどんどん大きくなる恐れがあります。ただし、一刻も早く害獣が居なくなってほしいからといって、自力で駆除するのは危険です。
この記事では、屋根裏に潜む動物の種類と見分け方や主な被害、駆除する方法、駆除する際の注意点などをまとめました。屋根裏の害獣を追い出して、もう二度と被害に遭いたくない方はぜひ参考にしてください。
目次
屋根裏に潜む動物(害獣)の種類と見分け方
屋根裏から「ドタドタ」「カリカリ」「カサカサ」「バタバタ」などの音が聞こえたときは、動物(害獣)が住み着いている可能性があります。
屋根裏に住み着く害獣は5種類で、それぞれ特徴が異なります。ここでは害獣の特徴を解説するので、ご家庭の状況と照らし合わせて、何が住み着いているのかを確認してみてください。
害獣は体格の大きさに関わらず、どれも危険な動物です!見た目はかわいい動物もいますが、放置すると危険なので、発見した際は早めに対処しましょう。
ネズミ

屋根裏に住み着いているネズミは、身体が小さい順に小さい種類からハツカネズミ・クマネズミ・ドブネズミです。
ネズミは非常に繁殖力が強く、わずか20日前後で妊娠・出産するため、1年で約1万匹も増えるといわれています。もし家でラットサインと呼ばれるネズミの足跡やかじり跡が見られた場合は、ネズミが潜んでいる可能性が高いです。
ネズミは柱や家具、食材だけでなく、配線をかじるケースもあります。配線をかじられたまま放置すると、火災の原因にもなるため非常に危険です。
| 体長 | ハツカネズミ:5~9.1cm クマネズミ:15〜25cm ドブネズミ:20〜28cm |
| 体重 | ハツカネズミ:10~20g クマネズミ:150~200g ドブネズミ:150~200g |
| 食性 | ハツカネズミ:雑食傾向いずれも昆虫を食べる クマネズミ:草食傾向 ドブネズミ:肉食傾向 |
| 足音の特徴 | 「カタカタ」「どたどた」と複数匹が走り回る音 |
| 足跡の特徴 | 前足が小さく、後ろ足が大きいちょんちょんと小さくたくさんついている |
| 鳴き声の特徴 | 「キーキー」「キュッキュッ」 |
| 糞の特徴 | ハツカネズミ:米粒のような大きさと形 クマネズミ:細長くて不揃いな形 ドブネズミ:先が尖った丸みのある形 |
ネズミの足跡や糞の特徴と画像で確認





イタチ

イタチはかわいい見た目をしていますが、実際は非常に凶暴です。イタチはとても小さな穴でもすり抜けて、家の中でも安全な屋根裏や床下に巣を作ります。
肉食動物で気性が荒いことから、ペットに襲い掛かる危険性があります。また、他の害獣と比べて、糞がかなり悪臭を放っているのが特徴です。
| 体長 | 20〜40cm |
| 体重 | 2kg以下 |
| 食性 | 肉食 ネズミやウサギ、ニワトリ、ハト、スズメなどがエサ 屋根裏で骨を発見することもある |
| 足音の特徴 | 「トントントン」と早く小さな音 |
| 足跡の特徴 | 猫に似ている5本の指と爪の跡がある |
| 鳴き声の特徴 | 「キーキー」「クック」 |
| 糞の特徴 | 他の害獣と比べ物にならないほどの悪臭 糞の量が性別で異なり、オスは多くメスは少ない |
イタチの足跡や糞の特徴と画像で確認


ハクビシン

ハクビシンは、額から鼻にかけて白い線が入っているのが特徴です。山里や市街地を住処としていて、家の屋根裏や床下のような人目につかない場所にも住み着きます。特に屋根裏の断熱材は、ハクビシンの格好の寝床です。
ハクビシンは繁殖力が強く、屋根裏に一度住み着いたらあっという間に繁殖するため、駆除するのが大変です。複数箇所に寝床を持つ習性があるため、2〜3日に一度音がする程度でもハクビシンが住み着いている可能性があります。
| 体長 | 40~60cm |
| 体重 | 2~5.5kg |
| 食性 | 雑食 |
| 足音の特徴 | 「ドンドン」と大きな足音 |
| 足跡の特徴 | 5本指 |
| 鳴き声の特徴 | 「カーッ」「キーッ」 |
| 糞の特徴 | 丸くて長い形種子がまざっている |
ハクビシンの足跡や糞の特徴と画像で確認


アライグマ

アライグマは、前足が器用で触覚に優れており、木登りが得意なため家の柱も登れる動物です。わずかな隙間を通ることができるため、家の屋根裏を住処にすることもあります。
見た目はかわいいですが、気性が荒くて危険性の高い性格です。攻撃性が強いため、近づくと噛みつかれる恐れがあります。アライグマは繁殖力が強く、オスは複数のメスと交尾して、メスは一度に3〜6匹の子どもを出産します。
| 体長 | 40〜60cm |
| 体重 | 3.5~11kg |
| 食性 | 肉食寄りの雑食 |
| 足音の特徴 | ドタバタするような大きな音 |
| 足跡の特徴 | 5本足で指が長い |
| 鳴き声の特徴 | 高い声で「クルルル」 |
| 糞の特徴 | 丸くて長い種子や動物の骨、昆虫の羽などが混ざっている |
アライグマの足跡や糞の特徴と画像で確認


コウモリ

国内でよく見られるコウモリは「アブラコウモリ」で、家に好んで巣を作ります。コウモリが屋根裏に侵入すると、壁などにコウモリの汚れが付着していることがあります。
春〜秋は活発になる時期で、羽の音が聞こえたときはコウモリが潜んでいる可能性が高いです。一度住み着くと、追い出してもまた戻ってくるようになります。コウモリはおとなしく噛みつくおそれはありませんが、菌やダニを持っているので直接触ってはいけません。
| 体長 | 4〜6cm |
| 体重 | 5~10g |
| 食性 | 虫中心の雑食 |
| 鳴き声の特徴 | 「キッキ」 |
| 糞の特徴 | パサパサしていて細長い虫の足が混ざっている |
コウモリの足跡や糞の特徴と画像で確認



屋根裏に潜む動物はどこから入ってくる?
屋根裏に潜む害獣の侵入経路をまとめました。
- 屋根裏や床下の通気口
- 換気扇部分
- 縁の下
- 屋根の隙間
屋根裏や床下の通気口は通常金網やフタで閉じられていますが、経年劣化によって穴が空いているとその隙間に害獣が入り込みます。換気扇は、使用していない間に進入される場合があります。
また、古い日本家屋にお住まいの場合は、縁の下や屋根の隙間に注意が必要です。数cmの隙間でも害獣は入り込んで来るため、見落としてはいけません。
家から追い出してもどこから入ったのか特定できないと、再び侵入されるおそれがあります。思いつく箇所は徹底的に調査しましょう。
屋根裏に住み着いた動物による主な被害
屋根裏に害獣が住み着くと、さまざまな被害を及ぼし、私たちの生活に影響を与えます。できるだけ被害が拡大する前に対応することが大切です。
屋根裏に住み着いた動物による主な被害を紹介します。
足音や鳴き声などの騒音
害獣は夜行性の種類が多く、夜になると天井から足音や鳴き声などの騒音が響き渡ります。正体が何か分からない不気味さによる不安で睡眠不足が続くと、以下のような症状があらわれ日常生活に支障をきたすでしょう。
- 不眠症
- 疲労感
- ノイローゼ
また、春になると害獣は繁殖期に入り子どもを産みます。子ども同士で遊んだり、頭数が増えるとさらに音で悩まされるため、ひどくなる前に対策することが大切です。
排泄物による悪臭
排泄物による悪臭は、屋根裏だけでなく生活スペースまで届くため非常に不快です。ハクビシンやアライグマは溜め糞という習性があり、決まった場所に何度も糞をします。そうして溜まった糞が悪臭を放ち、生活スペースにまで影響するのです。
害獣の悪臭に悩んでいる場合は、害獣そのものをまずは駆除しなければなりません。業者に依頼すると害獣を駆除した後に消臭・消毒もしてくれるので、まずは一度相談してみましょう。
住民への健康被害
害獣の身体には、必ずといってよいほどマダニやノミが潜んでいます。害獣のもつマダニやノミは屋根裏で広がるだけでなく、居住空間へ降りてきて人の身体に付着して吸血し、ダニ媒介感染症を引き起こします。実際に、肌のかぶれやアレルギー反応に悩んで害獣駆除の問い合わせをされたお客様がいらっしゃいました。
また害獣はさまざまな菌を持っており、万が一糞便に触れたり、かまれたりすると動物由来感染症にかかるリスクがあり大変危険です。
天井への被害

屋根裏に害獣が住み着くと、排泄物によって天井にシミがついたり、天井が抜け落ちたりする場合があります。実際に屋根裏に住んでいた害獣によって、天井が抜け落ちてしまったお客様がいました。そうなると、補修工事もかかって金銭的な負担が大きくなります。
また、壁の中で出産することもよくあり、そうなると壁を取り外すか点検口を設置して、手づかみで捕獲しないといけないため、一般の駆除工事にプラスして費用がかかります。放置すると死んでしまう可能性もあるため、出産シーズンを迎える前に対処しましょう。
【動物の種類別】自分で駆除する方法
害獣は種類に合わせた駆除をしないと効果は期待できないだけでなく、そもそも駆除が法律で禁止されている場合があります。
次は害獣の種類別に駆除方法を解説します。
ネズミを駆除する方法
ネズミは鳥獣保護管理法の対象外のため、以下の方法で自分で駆除できます。
- 忌避剤で追い出す
- 超音波で追い出す
- 罠で捕獲する
- 毒餌を仕掛ける
忌避剤や超音波にはネズミにとって居心地の悪い環境を作る効果があり、家に寄せ付けなくする効果があります。屋根裏に設置したり、スプレー剤を散布したりするだけなので、比較的簡単に取り入れられます。
またネズミ用の罠は、粘着剤を使ったネズミとりや毒エサが一般的です。ネズミが通る場所に設置しなければ意味がないため、糞の場所から経路を特定して罠を仕掛けましょう。ネズミは多くのダニやウイルスが付着しているおそれがあり、周囲に巻き散らかさないために捕獲したあとの消毒・除菌は必須です。
ネズミは1年中繁殖期です。1回の出産で6〜7匹の子どもを出産します。そのため、一度駆除しても、またすぐに再発する恐れがあります。
イタチを駆除する方法
イタチは鳥獣保護管理法により、狩猟免許や調査研究以外の目的で駆除するのが禁止されています。ただし、ニホンイタチのオスは自治体の許可があれば捕獲でき、狩猟期間内は自治体の許可がなくても捕獲可能です。
自分でできるイタチを駆除する方法は、基本的に追い出すのみで、以下の方法があります。
- 忌避剤を使用する
- イタチが嫌いなニオイを撒いておく
- 強い光を屋根裏に設置しておく
忌避剤はホームセンターで購入できます。用意できなければイタチが嫌いなニオイのハッカ油や木酢液、クレゾール石けん液、漂白剤で代用可能です。
また、イタチは夜行性なので光が苦手です。LEDライトなどの強い光で屋根裏を明るくすると自然と寄り付かなくなるでしょう。イタチを屋根裏から追い出した後は、消毒と除菌が必須です。
アライグマを駆除する方法
アライグマは鳥獣保護管理法で保護されており、くわえて特定外来生物のため自分で駆除できません。どうしても自分で駆除したい場合は、自治体で捕獲許可手続きをしてアライグマ捕獲器を借りるのも方法のひとつです。
自分でできるアライグマを屋根裏から追い出す方法は、以下のとおりです。
- 忌避剤を使う
- 超音波で追い出す
- 嫌な臭いで追い出す
他の害獣と同じく忌避剤や超音波でアライグマにとって不快な環境を作り、追い出すのもありでしょう。また、唐辛子やハッカ油、木酢液のようなアライグマが嫌がる匂いで追い出す方法もあります。追い出した後は消毒・除菌を忘れてはいけません。
ハクビシンを駆除する方法
イタチやアライグマと同様に、ハクビシンは鳥獣保護管理法で保護されており自分で駆除できません。そのため、以下の方法で追い出した後は侵入経路を絶って、二度と入ってこないように対策しましょう。
- 忌避剤や超音波を使用する
- 爆竹の音で脅かす
- 嫌な臭いで追い出す
ハクビシンは警戒心が強く大きな音を嫌がるため、近くで爆竹のような大きな音を鳴らすと驚いて逃げていく可能性があります。ハッカ油や木酢液などの嫌な匂いを使って追い出すのも、方法のひとつです。ハクビシンを追い出した後はウイルス感染やアレルギーを防ぐため消毒・除菌が必須です。
コウモリを駆除する方法
コウモリも鳥獣保護管理法で保護されているため、自分で駆除できません。忌避剤や嫌なニオイで侵入経路を絶ちましょう。
忌避剤はスプレータイプとジェルタイプがあり、いずれも換気扇やシャッターの隙間に散布すると効果的です。また、超音波を屋根裏など音が反響する場所に設置するとコウモリは近寄らなくなるでしょう。
また、コウモリの糞には「ヒストプラスマ」というカビが含まれており、人の肺に入ると感染症を引き起こす恐れがあります。糞や侵入経路に近づく際は周辺の空気を吸わないようにして、作業後は消毒・除菌を必ず行いましょう。
屋根裏の動物を追い出した後の予防法
屋根裏の害獣を追い出した後に再び住み着かないようにするために、侵入経路を防がなければなりません。害獣の侵入経路になりやすい場所には、以下の対策をしましょう。
- 金網のネットを設置する
- 家の隙間にパテを塗って通れないようにする
侵入経路は一ヶ所とは限らないので、家中くまなく確認する必要があります。実際に「忌避剤を使用して自力で追い出したものの、しばらくすると害獣が戻ってきた」とお問い合わせ時にお客様から相談を受けたことがあります。害獣には帰巣本能があり、一度屋根裏から離れた後にまた戻ってくるのはよくあるケースです。
害獣駆除業者に依頼すると入念なチェックのもとで侵入経路を特定して再発を防止できるため、同じ被害を害獣から受けたくない方は検討しましょう。
屋根裏の動物を駆除するときの注意点
市販の駆除グッズを使って屋根裏から動物を追い出すことはできても、本格的に駆除することはできません。次は、屋根裏に害獣が住み着いたときに知っておきたい2つの注意点をまとめました。
バルサンで屋根裏の動物は駆除できない
駆除グッズというとバルサンのイメージが強く、「害獣駆除にも効くのかな」と疑問に思っている方がいるかもしれません。しかし、バルサンは害虫駆除グッズであり、害獣には効果が期待できません。
屋根裏に害獣が侵入できるほどの隙間があるということは気密性が低く、バルサンの煙が外に漏れてしまうおそれがあります。機密性が低い場所で使用しても、バルサンの効果は期待できません。
もし害獣が逃げ出したとしても、バルサンには糞尿の臭いを消臭する効果がないため、マーキングのニオイを辿って再び屋根裏に戻ってくる可能性があります。バルサンには害獣を殺傷する効果がないため、追い出すことはできたとしても本格的に駆除するのは難しいでしょう。
市役所や保健所は害獣駆除をしてくれない
市役所や保健所に害獣駆除の相談窓口はありますが、実際に害獣駆除をしてくれるわけではありません。行政が対応してくれるのは、以下のとおりです。
- 害獣に関する相談
- 捕獲の許可
- 捕獲器の貸出
- 駆除業者の紹介
市役所や保健所に頼めば捕獲器の貸し出しをしてくれるものの、捕獲器を設置しても実際に捕まるとは限りません。また許可申請を受けなければ実際に駆除することはできないうえに、完全に駆除しなければ再び戻ってくる恐れがあるため、駆除業者にお願いする方が確実です。
屋根裏に動物が住み着いたときは専門業者に相談を
屋根裏に害獣が住みついて、自分で駆除できないときは専門業者に任せると安心です。専門業者に依頼すれば、感染症やケガ、再発のリスクを避けられます。
害獣を駆除するためには屋根裏に登らなければならないうえに、菌の感染や害獣に噛まれる可能性があり大変危険です。仮に駆除できたとしても、侵入経路をふさいだり、糞のニオイを除去したりしなければ再び害獣が戻ってくるでしょう。
一方で、プロに依頼すれば、侵入経路や被害状況を細かくチェックして適切な対応をしてもらえます。自力で駆除するのは確実でないうえに危険が伴うため、業者に依頼して確実に駆除してもらった方が安心して生活できます。
屋根裏が被害に遭った際に害獣駆除業者を選ぶポイント
害獣駆除業者選びのポイントは、以下の5つです。
- 無料で調査・見積もりを実施している
- 見積もりを依頼して料金を確認する
- すべて自社で施工している業者を選ぶ
- 再発保証制度がある業者を選ぶ
- 調査や作業の報告をきちんとしてくれる業者を選ぶ
それでは、害獣駆除業者を選ぶポイントを具体的に見ていきましょう。
無料で調査・見積もりを実施している
害獣駆除業者に依頼する際は、無料で調査や見積もりに対応してくれるところを選びましょう。
害獣駆除業者の中には、調査費用や見積もり作成費を別途請求されるケースがあります。調査や見積もりを依頼した後に費用を請求される恐れがあるため、事前に調査費用と見積もり作成費が無料かどうかを確認しなければなりません。
その際に、契約しなくても無料で見積もりをしてもらえるかどうかを確認するのもポイントです。なぜなら、契約する場合は見積費用が無料でも、契約しない場合は見積もり作成費用を請求する業者もいるからです。
まだ契約するか決断していない時点でお金を払うのはもったいないので、無料で調査・見積もりを実施している業者を選びましょう。
見積もりを依頼して料金を確認する
害獣駆除を依頼する際は、ネットに記載されている料金を参考にするだけでなく、見積もり依頼をして実際の料金を確認しましょう。害獣による被害状況や範囲、害獣の種類などによって対応が異なり、かかる料金も変動します。
ただし、見積もりで提示された料金が安い場合は工事内容が追い出しだけだったり、忌避剤を置くだけだったりと、簡単な作業しかしてくれない可能性があります。そのため、被害状況や対応方法の詳細まできちんと説明してくれる業者を選びましょう。
すべて自社で施工している業者を選ぶ
害獣駆除を依頼するときは、下請け業者に依頼せずにすべて自社施工の業者を選ぶと安心です。
業者によってはお客様対応は全てコールセンターに、見積もりは営業代行者に依頼し、サービスごとに異なる業者が請け負っているケースもあります。下請け業者に依頼すると費用の中に仲介手数料も含まれるため、お客様の金銭的な負担が大きくなります。
一方で、相談から施工まですべて自社施工の業者であれば仲介手数料はかかりません。
再発保証制度がある業者を選ぶ
害獣駆除をしても再び害獣が戻ってくるケースは多いため、再発時の保証制度があるかどうかを確認しましょう。再発保証がない業者の場合は、再発時に依頼するとまた同じように費用がかかります。害獣が再発するのは1年未満といわれているので、保証期間は3〜5年あれば充分です。
また、保証書がなければ保証期間がはっきりしないため、点検や再発の依頼時に業者とトラブルになるおそれがあります。業者に依頼した際は、きちんと保証書をもらうようにしましょう。
調査や作業の報告をきちんとしてくれる業者を選ぶ
被害状況や作業内容をきちんと報告してくれる業者なら、安心して作業を任せられます。屋根裏は自力で確認するのが難しいため、業者からの報告でしか状況を把握できません。
ごく一部ですが、実際よりも被害を大きく見せるために、他の現場の写真を見せて高額請求しようとする業者も存在します。そのため、写真だけで信用しない方が良いでしょう。
現地調査時や作業完了時に動画を撮って、その時点の状況を目に見える状態で報告してくれる業者だと安心です。
害獣駆除を業者に依頼したときの料金相場
害獣駆除の料金相場は、被害状況や害獣の種類により変動するため幅広く設定されています。
例えば、下記要件によって害獣駆除料金は大きく異なります。
- フンの量
- 屋根裏の被害状況
- 封鎖箇所の数
- 金網などの素材を加工する度合
- 建物の広さ など
害獣駆除を業者に依頼する際の参考として、弊社の参考価格を表にまとめました。
| 害獣の種類 | 害獣プロテクトの参考価格 |
| ネズミ | 9,800円〜 |
| イタチ | 12,500円〜 |
| アライグマ | 14,800円〜 |
| ハクビシン | 14,800円〜 |
| コウモリ | 9,800円~ |
作業内容によって料金が変動するため、この場で詳細をお伝えすることはできません。
ただし予算をお伝えいただくと、その範囲内で最大限の効果が出るように駆除する方法を提案いたします。
また弊社ではお客様に安心して利用していただくために、見積もりの際に必要経費を全て提示するので、作業後に追加費用を請求することはありません。
まとめ
屋根裏から「ドタドタ」「カリカリ」「カサカサ」「バタバタ」と聞こえたときは、動物が住み着いているかもしれません。音が聞こえるだけで姿が見えないからといって放っておくと、被害はどんどん広がっていきます。
天井が抜け落ちたり、住人の健康状態・精神状態にまで影響を及ぼすため、早急に対応する必要があります。屋根裏にいるのがネズミであれば自分で駆除できますが、イタチやハクビシンなどの害獣は法律によって自力で駆除できません。
駆除グッズを使って自宅から追い出せたとしても、再び戻ってくるリスクがあるため業者に依頼した方が早くて確実です。害獣被害でお困りの方は、害獣プロテクトにお気軽にご相談ください。
弊社はすべて自社で施工しており、現地調査やお見積もりも無料で実施しております。最長5年の再発保証付きなので、万が一再発したときも安心です。
なるべく早く屋根裏の害獣を駆除して、安心して生活できる環境を手に入れましょう。
\写真付きで安心!まずは無料で現地調査/